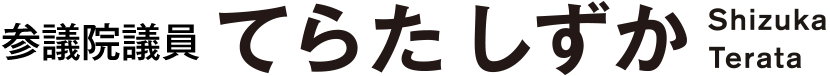ブログ
子どもが増えない理由は
2025.06.05 17:40

昨年の出生数は68万人台で、前年より4万人余り減少。統計開始以来、初めて70万人を下回りました。
1人の女性が産む子どもの数の指標となる合計特殊出生率は1.15となり、これまでで最も低くなりました(秋田県は1.04と全国平均以下)。
政府の想定以上に少子化が進んでいる現状を踏まえ、今回は子どもが増えない理由について、私の考えを(以前お話ししたことを改めて)お話ししたいと思います。
6年前、とある国会議員が「子どもを最低でも3人くらい産んでもらうようにお願いしてもらいたい」と発言し問題となりました。似たような発言は度々政治家から発せられ、繰り返し問題となってきました。これは政治家に限ったことではなく、日常の中でも、私を含め女性に対して「子どもはいないのか」、「一人っ子だと可哀想」という類の言葉は度々投げかけられ、その度にモヤモヤとした思いを持っていました。少子化なんだから当たり前と擁護する声も実は少なくないのですが、ここは丁寧に考えたいのです。
このような発言をされる方は、どちらかといえばご高齢の男性に多いように思います。おそらく、それはなんら悪気なく、彼らから見れば「小娘」のような年下女性に対して、アドバイスのように発せられているのだろうと想像できます。でも、彼らが望むように子どもが増えていかないのは、「小娘」達がアドバイスを無視しているからではないことをわかって欲しいのです。
私は思うのです。
日本の社会は長く、その「小娘」を蔑ろにしてきて、でも、その「小娘」たちしか命を生み出すことができないからこそ、その帰結として人口減少が進んできたのだと。
私自身も、祖母からずっとこのようなことを言われながらきました。
「勉強しろ」
「いい学校にいけ」
「いい会社に入れ」
そうしてある程度の年齢になると、
「仕事はいいから、もういい人を見つけて結婚しろ」
「結婚したら仕事は辞めろ」
「早く子どもを産め」
「一人っ子はダメ」
「早く二人目を〜」
こうして、「小娘」へのプレッシャーは絶えることがありません。
そしてさらにここ数年は、ちゃんとした育児との両立の環境を整えてもくれずに、仕事もして稼いで税金を納めて「女性活躍」しろ、というのはあんまりじゃないかと。私たち一人ひとりの人生には寄り添わず、単に経済を支えるコマとして見られているようで。
「子どもは少なくとも3人は産むように」と発言した方には、時に職場で女性たちは、こんなことを言われている事実を是非知ってほしいのです。
「新入社員が妊娠なんてありえない」
「妊娠は順番を考えて(先輩が優先。産休、育休の人が増えると職場が大変なので)」
「育休があけたと思ったらまた妊娠?(社員として)育ててあげようと思ってるのにタイミングを考えて」
「3人目(の育休)だって?犬じゃあるまいし」
これらは全て私が見聞きしたものです。
一方で、以前お話しさせていただいた15人ほどの会の中には、不妊治療に200万かけたが授からなかったという方がお2人いました。貯金がつきて、諦めがついた、とも。
私も結婚後4年、子どもを授かりませんでした。
子どもが欲しくても授からない人がいる。
誰もが妊娠する時期を選べるわけではない。
こんな当たり前のことが、きっと見えていないから、冒頭の発言が出てくるのだろうと思うのです。
こうした状況を作っている一番大きな原因は、やはり意思決定の場に女性が少ないこと、いわば「小娘」が、政治の世界に少なすぎるからだと私は考えます。
「私たち抜きに、私たちのことを決めないで」とは、障がい者施策に関して述べられたものではありますが、女性を取り巻く環境についても同じことを思うのです。
一人ひとりの女性が、もちろん男性も含めて、誰もが自分の価値観に沿って、かけがえのない人生を歩む中で、その1つひとつの選択がそれぞれ尊重され、よりよい人生を歩んでいくことが出来るように支援がなされる、そうしたことが実現されてはじめて、子どもを産み育てたいと思う人が増える国や社会になる、そうしなければ子どもは増えていかない。様々なライフステージを乗り越えてきた女性の一人として、強くそう思います。
少子化に悩む秋田において、子どもが増えてほしいという願いが高まることはごく自然のことと思います。
だからこそ、若い女性を取り巻く環境について、周りの方々には丁寧に、そして寄り添って考えて欲しいと思いますし、政治に身を置く一人の女性として、彼女たちのために頑張らなければと責任を感じています。
「男女は平等だって学校で言われてきた。でも、結婚して、子どもを持つことになったら全然そうじゃなかった。こんなのだったら、男女は不平等だって、学校で言われたほうがマシだった」
二人の子どもを育てる30代の友人にそう言われ、自分より若い世代の女性にそんなことを思わせてしまっていることに激しく胸を痛めつつ、容易なことではありませんが、日本と秋田が抱えるこれらの課題に関し、精一杯努力して参りたいと思います。