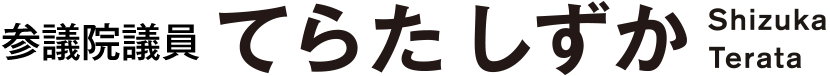ブログ
認知症の方と家族が安心して暮らせる地域づくりを
2025.07.06 12:26

昨日の遊説は大仙・美郷〜横手市内〜由利本荘でした。
横手の遊説では、祖母が晩年お世話になった浅舞のグループホームの近くも通りました。
昨年98歳で他界した母方の祖母は、なかなかの自由人の気分屋で、祖父とケンカをして家出をしたりしたこともあったそうです。母はそんな祖母に代わって、近所の方にお世話になりながら、弟の世話をしたりしていたとのこと。そんな過去もあり、私の母は、実母である祖母に対してはなかなか優しくなれないところがありました。認知症となり、生来のわがままに磨きがかかってくる祖母に対し、「母さん、そんな言い方するもんでね」と強く言う場面もありました。
私自身も、短期間ではありますが、祖母との生活の中で、どのような接し方がいいのかと悩んできました。「いつ結婚する?」などと同じ質問をなん度も繰り返されれば、応えるのも疲れてしまいます。母と祖母の関係を見ていて、血の繋がりがあるほうが互いに遠慮がないから大変だと感じたこともあります。祖母と自分、祖母と母、階段が登れなくなった祖母をおんぶして家の中に連れてきてくれた私の夫などとの関係性や様々な出来事を見つめる中で、認知症の方とそのご家族、ケアにあたる方々のご苦労や葛藤はいかばかりかと思ってきました。
2025年の今年、第一次ベビーブーム世代、約800万人全員が「後期高齢者」とされる75歳を迎えるのにあたり、日本では急速に高齢化が進展し認知症の方が増加しています。現在認知症の高齢者数は約470万人を超え、軽度認知障害の高齢者数は約564万人と推計され、合計すると約一千万人を超えています。高齢者の約3.5人に1人が認知症又はその予備軍と推定されます。
そんななか、ようやく認知症に関する初めての法律である「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が今年一月に施行されました。認知症の方が尊厳を保ちながら希望を持って暮らすことができるよう国や自治体の責務が定められています。計画の策定や施策の推進について、「認知症の方を含めた一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現を推進する」とされています。この目的に向けて、認知症施策を国や地方自治体が講じていくことになります。
全国でもトップの高齢化県である秋田に暮らす私たちにとっては、せめて10年前にやっておいてほしかったと思われるようなものでもあります。
昨年の秋には、大仙市にて行われた認知症フォーラムにて、「認知症とともに生きる地域づくり」と題したパネルディスカッションにも参加をさせて頂き、医療関係者や当事者の方ともお話をする機会を頂きましたが、県内でも、認知症に関する理解を深めるこうした機会は増えてきています。
認知症の方が暮らしやすい社会は、認知症ではない方にとっても安心して暮らせる社会。
親世代の全員が後期高齢を迎えた私にとっても、待ったなしの課題です。
全国に先駆けて高齢化が進行している秋田のようなところは、全国一律の制度では救われていかない、そのことをこれからも懸命に国政の場で訴え、対策を求めて参ります。多くの方の日々切実な課題となっている認知症対策がしっかりと進んでいくように、これからも当事者やご家族、支援者の方々からお声を聴きながら、共に社会ができる工夫や備えについて考えていきたいと思います。
写真は昨日での遊説の一コマ