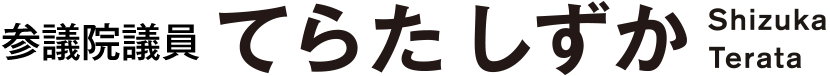ブログ
漁師さんの熱い想い
2025.07.07 19:34

本日は能代、八峰、藤里にお邪魔しました。
午前中に訪れた八峰町は民謡「秋田音頭」に登場するハタハタなどを水揚げする漁業が盛んな町。近年では岩館漁港で養殖する「輝サーモン」も有名です。
40回ほどにのぼった農林水産委員会の質疑では、県内の漁師の皆さんから様々ご意見ご要望を賜りながら、漁業に関することも度々取り上げてきました。
この4月の質疑で取り上げたのは、県魚ハタハタについて。ピーク時には2万トン以上あった漁獲が17トンにまで減り、県民に愛されるハタハタは、もはや簡単に手にすることができない魚になってしまいました。禁漁を経て回復していた漁獲量でしたが、再び危機的な状態に陥っています。ハタハタは単に県魚であるだけではなく、様々な食文化と結びついており、ハタハタがない冬の寂しさは言葉になりません。漁獲低迷の背景には、資源量はもちろん、まだ分からないことが多い生態の把握、近年の気候変動や海水温の上昇の影響など多くのことを知る必要があり、県単独で出来るようなことではありません。質疑では、こうした調査研究、原因解明への国の強力な支援を求めました。
また、「未利用魚」の活用促進について。未利用魚とは、サイズが不揃い、漁獲量が少ない、鮮度が落ちやすいなどの理由で、市場に出回らずに利用されない魚のこと。未利用魚の有効活用は、限りある水産資源の有効利用や漁業者の所得向上を図る上で重要な取り組みです。県内の漁師の皆さんも、様々な工夫をされていて、例えば、八峰町の若手漁師の方々は「漁師の分け前セット」として、水揚げされた様々な魚を詰め合わせてネット販売するなど、未利用魚の利用と収入の確保の努力をされています。国も後押しをしていますが、その支援を活用できる地域や対象となる魚種は限られています。気候変動の影響で獲れる魚は当然ながら変化を続けています。質疑では対象となる魚種を広げてもらい、意欲的な取り組みにさらなる支援をと訴えました。
私が農林水産委員会に所属した3年間の中でも、漁業に欠かせぬ漁港の価値、魅力を生かし、漁業体験活動や水産食堂などの海業の取組を推進し、交流人口の拡大とともに水産物消費の増進を図ることを目的とした法改正なども行われました。漁港だけではなく、内陸の道の駅や温泉など周辺地域が一体となって集客をする必要があることから、包括的に取り組みを支援できるようなものにしてほしいと求めました。
委員会で審議するにあたり、八峰町などの若手漁師さんたちにもお話を伺いました。「船の数も減って漁港も活気がない。このままでは駄目だと若手を中心にとても強い危機感があり、もう一度以前のように活気のある港をつくりたいという強い思いがある」と熱く語ってくださいました。
世界の中でも海水温の上昇が最も顕著であるとされる日本近海。農業だけでなく漁業も非常に厳しい状況にあります。それでも地元を愛し、漁業や漁村を盛り上げようと努力を続ける皆さんをしっかりと支援できるよう引き続き法律や制度を整えることに注力したいと思います。