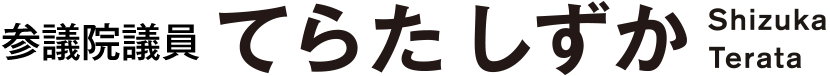ブログ
弟のこと
2019.03.03 22:59

「孤絶する1人、苦しむ1家族のために、99人が配慮する社会は作れないのか」
この問いは、私が取材を受けた本に載せられたもの。
そしてこの言葉は、私が望む社会そのものです。
そう強く思うようになった私の経験をお話ししたいと思います。
それは20年前に倒れ、亡くなった弟、茂之のこと。
弟は大学の講義の最中に倒れ、そのまま意識が戻らずいわゆる植物状態になり、1年3ヶ月の闘病ののちに亡くなりました。
以下、当時の記憶の一部をお話しします。
大学の講義の最中に倒れたとの一報。弟は埼玉の大学に通っていたため、
東京都内で働いていた私に母から連絡がきた。
病院に着くとすぐに救急の担当医から説明。到着時には心肺停止状態。
なんとか蘇生はしたものの、いつ急変してもおかしくない状態だと。
追って上京した母と共に、昼は病院にいて、夜は病院からの急変の連絡に怯えながら弟のアパートに帰る。
そんな生活をして5日後、重い表情の担当医に呼ばれた。
「一番危険な状態はなんとか脱した。が、意識が戻っていない。
心臓が止まって脳に血流がいかなかった時間が長く、大脳が不可逆的な変化を遂げてしまった。
残念ながらこの先、茂之くんの意識の回復は望めないだろう」と。
それ以降の言葉は覚えていない。隣に座る母の背中をさすりながら自分が泣き崩れてしまった。
遷延性意識障害。そんな言葉を、弟のことがあってから初めて知った。
いわゆる植物状態のことだ。
テレビで見ていると、植物状態というのはただ綺麗な顔で目を閉じて寝ている。
が、実際は、程度の差はあるものの多くのケースはそうではない。
少なくとも、弟には目を開いて宙を見つめ覚醒状態にある時と、目を閉じて寝ている時があった。
あくびをして顎が外れ、耳鼻科の先生が来てくれて元に戻してくださるまで数十分涙を流して苦しんだり、流動食がうまくいかずに戻してしまったり、痰の吸引などに苦しそうに顔をしかめ声なき声でもがいたり。
動かない体が硬直してしまわないようにリハビリをしてもらうが、運動をすることのない体はどんどん骨と皮だけになっていき、弟の脚は私の腕ぐらいの太さになった。
脳幹という生命維持を司るところのそばにあるという聴覚は最後まで残っていて「音は聞こえているので話しかけてあげてくださいね」と言われる。
事実、何か物を落としたりして大きな音がするとびくっと体を震わせる。
意識とはなんだろう。
弟はあちら側に行ったわけでもなく、かといって呼びかけにも答えてくれることもない。
植物状態から奇跡的に回復したなどの話を聞き色々と調べてみたり、文献を取り寄せたりするが、その都度わかったことは、そうしたケースは交通事故などの頭部外傷の患者さんであり、弟のように心停止によって脳の全体に血流が途絶えたケースとは違っていた。
調べれば調べるほど意識の回復は絶望的に思われ、語りかけをといわれても、弟の顔を見、骨と皮ばかりになった身体を見ては涙しか出てこなかった。
父も、そうした現実と向き合うことが辛いのか、病院に寄り付かず、朝から晩まで病院で過ごす母と気持ちがすれ違うばかり。
それぞれがそれぞれの悲しみで手一杯で、互いを思いやる余裕もなく、家族の気持ちがバラバラだった。
病院に朝から晩まで付き添っていた母は、弟の容体が安定すると、自宅での介護を望み、痰の吸引の仕方や体位交換の仕方などを習っていった。
とはいえ数時間おきのそうした処置やおむつの交換などを24時間つとめることは過酷で、在宅の間、母の体重は一時30キロ台になった。
容体が急変してまた病院に戻ると、母が少し休めるとホッとした。
母に一度、意識がないのだから、そんなにずっと病院にいなくてもいいのではと言った。
母まで倒れてしまうと心配だったからだ。
でも、母は「もしも一瞬だけ意識が戻って、その時に(家族が誰も)いなかったら?」と言った。
なんと残酷なことを母に言ってしまったのか。
当時の私は、母の気持ちを十分に寄り添うことができていなかった。
そのことを今でも後悔している。
母は、この状態が永続的だということを認めたくないということもあり、障害者手帳の交付などを受けることを一時拒んだ。
在宅の場合のベッドやたんの吸引の器具など、その度に補助を申請しても、なかなか適応にならないことも多かった。
死ぬことなどないだろう、そう思って19歳の弟にかけられていた保険から、高度障害で、死亡時と同じ額が一時金として支給された。入院費や在宅での看護介護のための費用に消えていった。
弟はこうして病院や在宅での看護、介護の末、徐々に全身の臓器の状態が悪化し1年3ヶ月の闘病ののちに亡くなった。
最期は臓器からの出血が止まらず、苦しそうな下顎呼吸を繰り返した。
「もうたくさん頑張った。もういいんだよ。ありがとう」家族で泣きながら声をかけ、病院のベッドで息を引き取った。
出棺の前、釘を打つように言われた私は、泣きじゃくり拒んだ。
父が火葬の挨拶の時に泣いた。
父の涙を見たのはその時一度きりで、きっとこれからもないだろう。
医療が発達し、弟のように、命は助かっても意識が戻らないというケースが増えているという。
弟の死から10年以上たち、何かで弟のことを知った河北新報社から取材を受けた。遷延性意識障害の患者家族の特集をしていたのだった。
後にその特集は一冊の本にまとめられ、取材にきた記者さんが送ってくださった。その本の帯に書かれていたのが冒頭の問い。
「孤絶する1人、苦しむ1家族のために、99人が配慮する社会は作れないのか」
今この瞬間も、介護と看護に明け暮れ、もしかしたら病院や行政の対応、制度や法律の不備に苦しみ、しかし声を上げる気力も体力もなく苦しんでいる方があることを知っている。
子育てに追われる日々の中、親、もしかしたら私の母のように、自分より遥かに若い子供の介護や看護に苦心し、親亡き後の子供の行く末を思い悩んでいるたくさんの人たちがいる。
こうしたケアワークは、特に家庭では、担い手は女性である場合がまだ多いーーー
弟が亡くなってから、こうした現実があることを知りつつも、弟のことを忘れたいがために仕事に没頭してきた自分がいます。
そうしたことに今も罪悪感を覚えながら、、この現実と悩みの切実さを知る一人の女性として、そうした声なき声の代弁者であれたらと強く願い、今回、自分自身が政治に向き合ってみたいと考えました。
個人的なことは政治的なこと。政治に向き合うことを決めた時に友人から贈られたこの言葉を噛み締めながら歩みたいと思います。
写真:小学生の頃の私たち兄弟