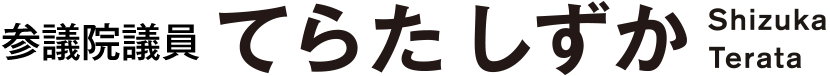ブログ
今いる子どもたちを大切に
2025.07.12 15:17

少子化は秋田と日本が抱える最大の課題です。
でも、私は「少子化対策」という名称ではなく「家族政策」と呼びたいと思っています。
子どもを育てるには、経済的な余裕と、加えて、日々の子どもの成長を感じ喜ぶことができる時間の余裕も必要です。
そしてとりわけ、一人ひとりの個人の選択を尊重する社会でなければなりません。
就職や結婚、子育てを経験する人生の繁忙期を徹底してサポートし、子どもを持ちたいと思う人がそれを叶えられるための、住宅支援、控除や手当で、子育て世帯を支えていく必要があります。
日々の子どものちょっとした成長、初めての微笑み、初めての発語、初めての伝い歩き・・・こうしたことで幸せを噛み締めるには、時間の余裕があることが前提であり、そのためには更なる働き方の改革によって、「親である時間」を男女ともに確保することが大切だと思います。
また、どんな子どもが生まれても、それは障がいがあっても、発達障がいがあっても、不登校になっても、親が自己責任として覚悟を持って仕事も辞めて全てを背負わなくてはいけないような社会のあり方を変えていかなければなりません。
私がこのことに気付かされたのは、障がいのあるお子さんを抱えて海外に引っ越した方からお話をお聞きしたときのことです。
そのお母さんは、海外の保育園にお子さんの受け入れを頼みにいき、「頑張りますから、どうかよろしくお願いします」と挨拶をしたところ、「いえいえ、お母さんは頑張らなくて良いんですよ。そのために私たちがいるんですから」と声をかけられて、その場で泣きだしてしまったのだそうです。「日本にいるときはいつも『お母さん頑張りましょう』と努力を求められてばかりだった。『頑張らなくていい』と言われたのは、思えばこの子が生まれてから初めてだった」と仰っていました。
一方、その一年ほど後に、とある省庁の方と議論をしていたら、ご自身のお子さんに障がいがあるとして、こういう子どもを持ったら「親が覚悟を持って育ててほしい」と仰っておりました。当事者として重い告白をして頂いたことに感謝をしながら、それでも私は、親が覚悟を持たなくてはいけないような現状こそ変えなくてはいけないと感じました。
障がいがある子ども、日常的に医療的ケアが必要な子どもが生まれたら、母親が仕事を辞めて、人生の全てをその子のために捧げなくてはならないような現状を変えなくてはいけないと改めて思いました。
子どもに障がいがあれば、その子は将来働くことが難しいかもしれない、その分、自分が働かなければならないのに、通院・療育・学校への送迎や付き添いで満足に働くことも叶わない、そんなお声をたくさん聞いてきました。また、男女の賃金格差が大きく、子どもを抱えていたらまともな給料を得られる仕事にも就けず、そして子どもを抱えて離婚したらその半数が貧困に陥る現状があります。こうした、子どもを持つことがリスクとなるような国では、子どもは増えていかない、そう強く思います。
どんな子どもが生まれても大丈夫、地域に支えられながら頑張らなくても生活をしていける、子どものことだけではなくて、一度きりの自分自身の人生も当たり前に楽しむことができる、そして子どもが巣立ったら豊かな老後が待っている、多くの方がそう感じられる社会を作っていかなければならないと考えています。
日本は少子化に悩みながらも、こうした困難を抱えた子どもたちや保護者への支援は手薄なままです。そしてまた、虐待相談件数も過去最高、子どもの死因のトップは自殺と、実は子どもを大切にしていない、子どもたちを取り巻く環境は恵まれているとは言い難い現状があります。今いる子どもたち全員を大事に出来なくて、何が少子化対策なのかと、政策のあり方に憤りを覚え、小さな運用変更から大きな制度設計の提案まで、懸命に変える努力をしています。
医療的ケア児者議連、児童養護議連、インクルーシブ議連、多様な学び議連、自殺対策議連とその中におかれた子ども若者自殺対策PT、ママパパ議連・・・子どもたちを取り巻く課題について多くの議員連盟に参加をして議論しながら、すべての課題は地続きであることを実感しています。子どもを支えるには、子どもを育てる家族を徹底的にサポートすることが必要です。
子どもを持ちたいと思う方が増えていく社会にするには、「少子化対策」と看板を掲げるのではなくて、今いる一人ひとりの子どもたちとその親たちが幸せを感じられるようになる「家族のための政策」を、一つひとつ、充実させていかなくてはいけないと思っています。