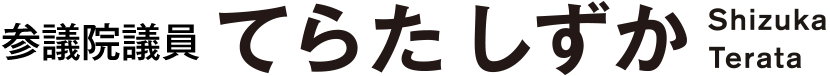ブログ
不登校経験者として
2025.07.14 17:29

子育ては生きがいとなる一方で、苦労は絶えません。
我が子はおかげさまで11歳になりました。小学校の先生には、「〇〇くんは悪気なく人の話を聞いていないですね。本人には悪気がないので注意しても直らない」などと言われ、冷や汗が出ることもありますが、入学してすぐにコロナ禍での休校があったのにもめげず、日々色々ありながらも元気に楽しく学校に行ってくれていて親としてはホッとしています。
私自身は、中学生の頃に不登校、高校を中退して大検をとって大学に進んでいます。当時の私が苦しんだように、学校という枠にうまく馴染めない子どもが「自分はダメなんだ」と思い込んでしまう社会を変えたい――その思いが、私の政治の原点です。
すべての子どもが、自分らしく学び、育つことのできる環境を整えたい。そして、学校に馴染めない我が子を抱えて悩み苦しむ保護者たちを支えたい、そうした思いから、フリースクールなど、学校以外の学びの場への支援拡充に取り組んできました。学び方は子どもの数だけ存在し、その選択肢を保障することは、子どもの生きる力を育てることにつながります。ただ、そうはいっても、子どもも保護者も、近くの普通の学校に楽しく通えるようになることが一番ラクなんだとも思います。そのため、すべての学校が、一人ひとりの子どものありのままを受け止める場へと変わるよう求めています。特に秋田のようなフリースクールなどの選択肢が限られている状況のもとでは特に、公教育がどのような子どもも受け止める場所となることが重要です。
超党派「多様な学びを創る議員連盟」のメンバーとして、自身が不登校だった時の心の苦しさを他の議員に共有し、学校の変化と学校外の多様な学びの場への支援を政府に求めていますが、不登校は減るどころか、子どもの数が減る中でも増え続けて、小中高合わせて過去最高の42万人となり、かつての当事者として、そしていま国政の場にある一人として現状に忸怩たる思いがあります。
秋田においても、「『まなび』を考えるネットワーク」の立ち上げに参画し、不登校や虐待、障がいのある子どもの教育など、幅広い課題に向き合う仲間80名の方々と共に、子どもの最善の利益を軸にした教育のあり方を探っています。
学校に馴染めない、学校が変わってほしいと思いながら不登校に悩む子どもたちは、その一人ひとりがこれからの教育を変えていくパイオニアだと思っています。
これからも、今の教育の中で見過ごされがちな子どもたちの声に寄り添い、一人ひとりのありのままを受け止める学校づくりと、学校外の学び育ちの場への支援を充実させるため、活動を続けてまいります。