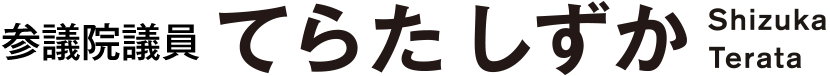ブログ
すべての命が「おめでとう」
2025.07.16 17:12

日本には様々な事情によって親もとで暮らすことができず、社会的養護と呼ばれる制度のもとで生活している子どもたちが約4万2千人、秋田にも約200人います。私は、どこで生まれ、どんな状況にある子どもたちにも温かい家庭が与えられるべきであると考え、6年前の初当選直後から超党派児童養護議連に所属して努力を続けて参りました。
親もとで暮らすことができない子どもたちは、日本では7〜8割が施設で暮らしています。しかし、特に0歳から2歳までの乳児期に施設で集団養育されると、その子の心身の健康や人間関係の構築に長期にわたって好ましくない影響を与えることが、多くの研究から明らかになっています。もちろん、各養護施設のスタッフの方々は日々献身的に子どもを守り育て慈しんでおられ、私も感謝の気持ちでいっぱいです。ただ、それは特に幼少期、長期に渡ることはあってはならないと考えます。国連も施設ではなく、家庭養育を原則とするよう日本に求めており、2016年には児童福祉法が改正され、里親等への委託率を大幅に引き上げる方針が掲げられました。しかし、現実には全国の里親委託率は25.1%(2023年度末)にとどまっています。
私が議員となった年の資料で秋田の里親委託率は9.6%(2017年度末)で全国最下位でした。私も危機感を持って勉強し、厚労省やこども家庭庁の方から分析などを聞き、毎年の語る会でこのことに言及し、また、秋田の事務所で里親セミナーを開催するなどしてきました。全国最下位だった委託率は今、25.5%となり、全国の中位に上がってきました。発信を続けて光があたるようにと努力をしてきましたが、ひとえに現場の関係者の方々の努力と、里親さんの献身的な働きのおかげです。これは単なる数字としての成果ではなく、子ども一人ひとりに家庭が出来、将来も頼れる実家のような繋がりが生まれる可能性が出来たことを示唆しています。
子どもたちは、決して平等な環境に生まれてくるわけではありません。虐待、貧困、親の病など、さまざまな逆境体験を背負いながら成長を余儀なくされている子どもがたくさんいます。だからこそ、社会全体で子どもを育てる視点が必要です。昨年11月、県内に進出している企業の方から、地域貢献のアイデアはないかと聞かれる機会があり、施設や里親家庭で暮らす子どもたちが進学する際の奨学金を出してもらえないかとお願いしてみたところ、二つ返事でご了解を頂きました。県内各地の養護施設や里親会の方、県議会の方などからもご意見を頂き、弁護士らのボランティアの参画も頂いて、社団法人を立ち上げ、この春から支援を始めています。親もとで暮らせない子どもたちの存在を知り、理解し、関わる人が増えることが、子どもたちの未来を変えていく力になると私は信じています。
当然のことながら、家庭を支える、という視点も忘れてはいけません。この世に生を受けた子どもたちが、なるべく社会的養護のもとに入ることなく、親もとで暮らせるのが一番であることは論をまちません。
「もしあの時、うちの母を助けてくれる人がいたら、僕は自分の家で育つことができていたかもしれない」。この言葉は、里親のもとで育った青年が語ったものです。彼は施設に保護された後、温かな家庭に迎えられ、今も里親と良好な関係を築いていますが、実の母親が適切な支援を受けられていたなら、自分は家庭を離れずに済んだかもしれないという悲しさをにじませていました。フランスでは妊娠期から家庭に寄り添い、子育てに不安を抱える親に制度的な支援を届けています。子どもを助けるためには、親を、家庭を支援する。私が妊娠期からの継続的な育児支援、家庭支援の充実を訴えるのは、これが虐待や養護の必要性そのものを減らす大きな力となると信じているからです。
虐待のニュースを見るたびに、我が子が1〜2歳だった頃の、育児を振り返ります。夫は産後から今も育児に懸命に取り組んでいますが、当時は多忙を極めていました。東京にいる間、私は孤独な育児に苛まれ、声を荒らげたり叩いたりするよりはましと、追いかけてくる子どもから逃れて、トイレに閉じこもり一人で泣いていたこともありました。ニュースになっていたのは私だったかもしれない、そう思うこともあります。この実感があるからこそ、子どもを一人残さず守るために、支援の拡充と、すべての親に支援の枠組みを広げておく必要性を痛感しています。
今年5月、この6年の取り組みを見ていただいていた方々にお声がけを頂き、代々木で開催された全国里親研修会のシンポジウムのパネリストとしてお招きを頂きました。6年前のこの研修会への参加が、この分野をライフワークとして取り組むことになった一つのきっかけでもあったことから、とても感慨深く、さらにこの分野に尽力をとの思いを新たにしています。
すべての命が「おめでとう」と迎えられ、どんな環境に生まれても、大切に慈しんで育てられる社会を目指して。子ども一人ひとりの人生を支えるために、子どもを育てる家庭を支えるために、これからも行動していきたいと思います。