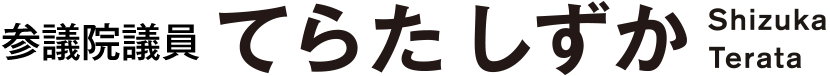ブログ
最善を手繰り寄せる努力
2025.07.19 20:34

17日間にも及ぶ選挙戦が最終日を迎えました。
多くの方から叱咤激励を頂いた日々を振り返りながら、最後の訴えをここでお伝えしたいと思います。
17日間という長い選挙戦、全県各地を走り回ってきました。
選挙カーで住宅地や集落をくまなく回っていると、多くの県民の暮らしぶりに改めて触れることができました。
高齢化、老老介護、暮らし向きの厳しさ、過疎化と空き家の多さに胸が痛み、
とりわけ農村、漁村の一層苦しい状況が目に入ります。
もし政治がしっかりしていたら、もっと農政が家族農家、小規模農家、兼業農家、漁業者を支えていたら、地域からこんなに人は出ていくことはなかったのではないかと胸が潰れる思いがしました。
いまの現状を見るにつけ、募る想いがあります。
私は悔しいんです。
秋田は、食料も、エネルギーも、子どもたちも全部都会に送り出し、
この秋田での暮らしは苦しくなるばかり。
東京一極集中の流れは全く変わっていません。
このことは、県民に責任があるのではありません。
県民の一人ひとりは置かれた環境の中で精一杯の努力をしながら日々を暮らしています。
米の価格についても、ほんの一年前まで、農家の皆さんは長く米価の低迷に苦しみ、
赤字では続けていけない、先祖代々の農地を守っていきたいけれども間に合わない、
とんとんなら何とかやれるけど赤字では無理なんだ、子どもには継がせられない、大規模化とスマート化だけでは農地も集落も守られないと訴えていました。
その時にはなんの有効な対策も取ってくれなかったのに、
米価が高騰した途端、備蓄米を大量に、最後には価格まで指定して市場に出しました。
遂には、足りなければ輸入も選択肢というようなことまで言い出して、
農家の方々は、今までの自分たちの苦労はなんだったのかと、頭が真っ白になった、もう自分たちを振り回さないでほしいと静かな怒りを抱えています。
あまりにも生産者の声が、生産地の苦労がないがしろにされていると感じます。
そして、いま、米価格だけではなく、あらゆる物の物価が上がり、
個人のやりくりや我慢でどうにかできる限界は超えています。
年金生活を送られている皆様の生活、もともと厳しい生活を送っていた方の暮らしがさらに追い詰められている。
昨日も、生活が苦しいんです、と涙ながらに私の手を握り訴えてくださる方がありました。
政府は補正予算・本予算と巨額のお金を使ってきましたが、その一つでも県民に直接届いたものがあったでしょうか。
私は、このような地方の地域の声を聞かない、生活の実態を顧みない政治のあり方を転換したい、
もっと生活に根ざした、生活をしていて納得感のある政治を実現していきたいのです。
秋田と日本の抱える最大の課題である少子化も、全く改善の方向に向かっていません。
その原因は、政策の立脚点が間違っているからだと思います。
今の政治は、女性に「産めよ増やせよ」と強く働きかけているように女性の私には感じられ、そのような無言の圧をかけてくる社会を嫌って、女性たちは子どもを持とうという気持ちが失せているのではないでしょうか。
当たり前のことですが、女性は国のために子どもを持つのではありません。
一人ひとりがかけがえのない自分自身の人生を歩いています。
自分の人生の中で、子どもがほしい、子どもを今なら持てる、育てていくことができると思った時に、運よく授かることができた人だけが、子どもを持つことになる。だからこそ、女性たちが、子どもを持とうと思うには何が必要かを寄り添って考えなければならないのに、今の国会は、家事・育児・介護を全て誰かに丸投げをして仕事だけに専念をしている男性たちが多くを占めているがゆえに、そのことに気づくことすらできていません。
子どもを育てるには、経済的な余裕が必要です。
併せて、日々の子どもの成長の喜びを感じることができる、時間の余裕も必要です。
そしてとりわけ、一人ひとりの個人の選択を尊重する社会が必要です。
就職や結婚、子育てを経験する人生の繁忙期を、徹底してサポートする必要があります。
子どもを持ちたいと思う人がそれを叶えられるための、住宅支援、控除や手当で、子育て世帯を支えていく必要があります。
日々の子どものちょっとした成長の喜び、初めての微笑み、初めての発語、初めての伝い歩き・・・こうしたことで幸せを噛み締めるには、時間の余裕が必要であり、そのためには更なる働き方の改革によって、「親である時間」を男女ともに確保することが大切です。
また、どんな子どもが生まれても、障がいがあっても、発達障がいがあっても、医療的なケアが必要であっても、不登校になっても、親が自己責任として全てを背負わなくてはいけないような社会のあり方こそ変えていく必要があります。
子どもがもっと増えていく社会にするには、「少子化対策」という看板を掲げるのではなくて、今いる子どもたちと子育て世代が幸せを感じられる「家族のための政策」を一つひとつ作り上げ、実行に移していく必要があるはずです。
国会にはまだあまりにも育児の実態を知る人が少ない、だからこそ、的外れな政策が作られては消え、消えてはまたおかしなものが出てきて、若い世代、特に女性たちをげんなりとさせています。私たちのことを、私たち抜きで決めないで、というのは障がい者政策に関して言われていることではありますが、私は女性についても同じことを思います。
どうか、お力を貸してください。
家事、育児、介護、生活の実態を知る一人の女性として、
そして県内ではいまだ唯一の女性国会議員として、
県民の思いや苦しみに寄り添い、声なき声に耳を澄ませ、
それでもなお、私にも届かない声があることを胸に留めながら、
生まれ育ったこの秋田と、子どもたちの未来のために、
一生懸命力を尽くして参ります。
皆様の生活に伴う困難の一つひとつに最善を手繰り寄せる努力を、国政の場で続けて参ります。
どうか皆様から最後の最後までご支援の輪を広げて頂きますことを心からお願いし、私からの最後の訴えとさせて頂きます。
本当に有難うございました。