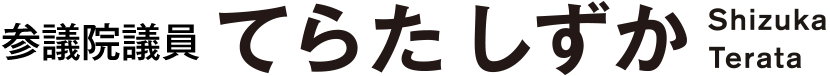ブログ
当選後の初公務
2025.08.06 16:25

参議院選挙直後の臨時国会は閉会いたしましたが、公務は国会の状況に関わらず多岐にわたります。
それは選挙直後も変わらず、初めての公務は国会開会前の先月26日、秋田市で行われた東北地区里親研修会秋田大会でした。
この会は、何らかの事情で親もとで暮らせない子どもたちを養育する里親さんたちが1年に一度集まり、子どもの養育について学んだり、当事者同士の情報交換をしたりするものです。
2日間にわたり行われた今回、初日の前半は、県医師会長でもあり、こどもの心と発達クリニック院長である小泉ひろみ先生、全国里親会会長の河内美舟様のご講演があり、後半は聖霊短期大学の先生方から、子どもの育ちについて、睡眠や食事の役割と重要性、発達段階における課題などの最新の知見を学ぶことができました。
小泉先生からは、子どもの話を聞く手法としてのオープンダイアローグ、また、物事を視点を変えて捉え直すリフレーミングなどについてお話がありました。先生のお話をお聞きしながら、ふと、我が子のひと言を思い出しました。それは、学校でのトラブルで、お友達から突き飛ばされたという話を他のママから聞かされた時のこと。学校帰りにもそんなことは言っていなかったけどなと思いながら本人に話を聞くと、「別に痛くなかったから大丈夫。@@(友達の名前)は本当は優しいんだよ。でも、その優しさを発揮する方法がわからなくて困ってるんだ」と言ったのでした。突き飛ばされる、という嫌な出来事に遭遇してもなおそんな風に捉えられるのは優しいね、と本人に言ったのでしたが、実はリフレーミングをしていたのだな、「突き飛ばす怖い子」、ではなくて、「優しくしたいけどどうしたらいいかわからなくて困っている子」と捉え直していたのだなと気付かされ、帰宅してからそのことを伝えて誉めたのでした。
聖霊のお二人の先生は、それぞれが現役の子育て中のパパでもあり、それぞれ子育てをしながらの実体験なども盛り込まれたお話は、同じく子育て中の私としても、公私共に非常に大変学ぶところの多いものでした。また、共働きが増える中でも、いまだ家事育児などが5.5倍女性に偏っているとされる日本において、若い世代の男性であるお二人が子育てをしながら研究や教育に従事されていること、それぞれ実生活からの学びを仕事にも活かされている様子を教えて頂いたことは、未来への希望が感じられ、大変嬉しいことでもありました。
2日目は、県南に住む里親さんと里子さん(既に成人)のこれまでの歩みやこれからの活動に関するお話と、東北各県の里親会の会長から、それぞれの地域の活動と課題に関するお話がありました。実際の親子間であっても、反抗期や思春期の葛藤などは親子共に疲弊をするものですが、里親子の関係では更に難しさがあるだろうということは想像ができます。そうした葛藤をそれぞれその時々でどう過ごしてきたのか、今振り返ってどう思っているのかなど、赤裸々にお話をいただいたことは、現役で里親活動をされている方々にとって大きな励ましと学びがあったことと思います。また、東北各地の、里親登録を済ませながらもまだ子どもの委託を受けていない未委託里親さんの交流会の取り組みや、様々な趣向を凝らした里親さん・里子さん同士の交流会などが紹介されると共に、課題として、里親会の会員をどう増やすか、資格更新時の手続きに関することなどが話し合われました。私としても、国としてできること、更新手続きに関しては国として最低限求めていることなど、東京に戻って改めて確認したいと思う課題をいくつかお預かりしました。
日本では、全国で約4万2000人、秋田にも約200人の子どもたちが実親のもとを離れ、社会的養護と言われる制度のもとで育っています。そのうち、施設ではなくて里親さんに委託されているのはまだ25%と4人に一人という状況で、国際機関からは、「施設養育はいますぐ止めるべき」との勧告を受けています。幼い頃から施設で育つことは、適切な発達を妨げ、将来にわたり心身に大きな影響を及ぼすことも多くの研究から明らかとなっています。
県里親会の高橋会長からは、「本来、里親の役割というものは全身全霊で子どもの養育に当たることであって、制度改正の要望を行うことではない。十分に整った制度・環境の中で、子どもの養育だけに向き合うことが本来のあるべき状態であるが、未だそうはなっていないからこうした活動をしなくてはならない」との趣旨のお話があり、本当にその通りと胸にずっしりと受け止めました。家事育児が女性に偏るなか、育児の実態を良く知る議員がまだ少数派である経緯から、こうした子どもに関する課題はあまり光が当てられず放置をされてきたと感じています。これからも社会的養護を取り巻く様々な課題、里親制度の普及啓発のため、人生の最初に大きな困難を抱えることとなった子どもたちのために、関係者機関や関係者の方々から学びながら、子どもたちの最善の利益のために働いていきたいと思います。
ここからの6年間、こうした社会の中で弱い立場に追い込まれる子どもたち、女性、ご高齢の方、障がいのある方、何らかの理由で少数者と呼ばれる方々のことにとりわけ注力をしながら活動を続けて参ります。
*写真は当選証書を拝受した時のもの。