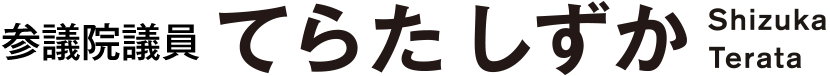ブログ
不登校児だった私から
2019.04.18 10:52

子どもにとって、学校とは。
親として、また、政治を目指すものとして非常に重要な問いです。
先日「与党の審議拒否は登校拒否みたいなもの」と立憲民主党の枝野代表が発言し、直後に撤回、謝罪とのニュースがありました。
かつての不登校当事者として、いつかは語りたいと思っていたテーマでもあり、今日はこのことを。
はじめに・・・不登校の経験者として、この発言は大変悲しくなりました。「登校拒否」という言葉自体も目にすることが少なくなってきていた昨今(今は文科省も「不登校」と呼んでいる)、「与党の審議拒否」という言葉に引きずられたものとはいえ、このような文脈の中で使われ、また、多様な教育を後押ししてくれるであろう党の代表からの言葉であることが、過去の当事者として、とても残念です。
今後の学校のあり方、教育のあり方という、日本にとって最も大事な議題の一つを考える上で、基礎となっている私の過去をお話しします。
私自身は、小学校3年生で秋田から青森へ、そして6年生で茨城へ、父の仕事の都合で引越しをし、中学校3年生の時に、父が転職をして、生まれ故郷である横手に戻りました。私が高校に入ってしまえば転校は支障が大きいだろう、いずれは故郷に戻りたいからと、父はそのタイミングで転職を決意したのでした。
中学3年の5月、転校初日。先生から、この学校ではその前髪はもう少し短い方がいいとか、スカーフの結び方が変と笑われたりしながら校内を案内されました。クラスの皆の前で挨拶をすることには慣れっこになっていた私でしたが、職員室でも挨拶をするように促されました。職員室は大きく、前の学校の倍、ひと学年8クラスあるマンモス校でしたので、それには緊張しました。名前を名乗り、よろしくお願いしますと頭を下げると、頭の下げ方が足りないと言って、「頭はこうやって下げるんだ!」と、先生が横から私の頭を手でつかんで押し下げました。
その後も、問答無用ですぐに怒鳴ったり叩いたりする先生方がいたり、ムチのようなものを持ち歩く先生までいたりして、私は完全に萎縮しました。私には違和感しかないそうした風景でしたが、他の同級生たちには違和感が無い様子。思えば転校生の私以外の生徒には、入学当初からそれが当たり前だったのですから、無理もありません。が、当時の私は、私だけが感じているように見える違和感、疎外感が次第に膨らみ、苦しくなっていきました。
転校前の茨城の中学は、当時新設したばかりの学校で、子どもと人間同士の付き合いをしてくれるように感じる先生が多く、その落差がショックだったのだと思います(大人になった今思えば、横手の先生たちも、マンモス校の中で、たくさんの生徒を管理することに手一杯だったのだろうと、その大変さを振り返ることができます)。
秋。大好きだった祖父が亡くなり、忌引き明けで登校した11月初め、校門指導をしていた先生から「ズル休みするなよ」と声をかけられました。この時、私はもうこの学校に行くのは止めようと決めました。私が何があって休んでいたのか事情を知ることもなくかけられた一言で、これまでなんとか耐えてきた糸がぷっつりと切れたのでした。
この学校にいたら、私が私ではなくなる。そう感じ、その翌日、思い切って両親に「もうこの学校に行きたくない」と告げました。「わかった。じゃあ、お父さんが今日先生に会って、もう学校には行かないと話してくるから、とりあえず上履きなどを引き上げてきなさい」との父の言葉。「ずっと元気がないから心配していた。何より一番あなたが大事。学校なんて行かなくていい。静が一番大事だから」と母。当然ですが、両親もきっと、学校に行かない我が子が心配だったろうと思います。それでも、父は私を守り、母はことあるごとに、「人生はいい時も悪い時もある。静は大変な時が最初にきているだけ。だからこれから楽しいこと、いいことがたくさんあるよ」と言って、世間体より何より私が一番大事なのだということを態度で示し、私を信じて待っていてくれました。
その後、卒業式も含めて登校することなく卒業。勉強自体は嫌いではなかったので、高校に進学しました。
高校進学後、友人たちと楽しく過ごしていましたが、服装検査という名の下に行われる髪の毛、服装、持ち物のチェックにまた違和感を覚えました。先生たちは、外見だけをあれこれいうけれど、私たちのうわべだけで、中身には興味をもってくれていないんだな、私たちが何を考えているかなんて関心がないんだ。そう感じられて仕方がなかったのです。
2年生への進級を控えた進路指導。就職希望でも成績が良ければ大学進学クラスへ、成績が悪ければ、進学希望でも大学進学クラスでないクラスを勧めてくる先生たちの指導に反発を覚えました。どうして希望を尊重してくれないのか。成績という物差しでしか自分たちをはかってくれないことが悲しい。そう思い始めたら、また色々な先生たちの言動に感じる違和感が耐えられないものになっていきました。大学には進学したいと考えていたので、そのための大検取得を支援する予備校があることを知り、高校2年の秋、母と共にそこに相談に行きました。
「すでに高校2年の出席日数は足りている。このまま出席しなくても、期末試験を受ければ高校2年の単位までは取得できる。そうすれば、大検(現在の高校卒業程度認定試験)で取らなければいけない科目はあと3科目。大検は、レベルで行けば中学校くらいの勉強がわかれば大丈夫。こんなところ(大検予備校)にお金を払わなくても、自力で勉強すれば合格できる」。
こんなとても親切なアドバイスをもらい、それに従って、高校3年5月に中退。不良だったわけでもない、特に問題を起こしたわけでもない私は、先生たちに最後まで、どうして辞めるのかわかるように説明してほしいと求められました。が、私も、当時私自身の言葉で自分の違和感を説明することができず、最後には、大検の申し込み期日までに高校を辞めていないと出願ができなくなると頼み込んで辞めさせてもらいました。先生からは、大検がダメだったら戻っておいで、補習をして、みんなと同じ時期に卒業させてあげる。そう耳打ちされました。
高校中退後、既に転勤されていたかつての恩師に手紙を書きました。その恩師からの返信には次のように書かれていました。
「学校に違和感を感じているのはあなただけではない。私もあの服装検査がとても嫌だった。そうした管理教育臭に嫌気がさし、定年を2年残して、私も学校を辞めました」と。
大学に入り、不登校の本をいろいろ読み漁りました。上記に書いたようなその時々の私の気持ちは、当時そのように言葉で表現できていたか自信がありません。ただもやもやと、この学校には行けない、行きたくない、私が私らしくいることができなくなる、でも、みんなは行けるのに、行けない私がやっぱりどこかおかしいんじゃないか、などと思っていました。自分で学校に行かないと選択をしたのにも関わらず、漠然とした大きな不安に苛まれ落ち込んでいました。我が家は両親に格段の理解があったのにも関わらず、です。のちにボランティアとして関わることになる、東京シューレというフリースクールの学生ゼミにも参加しました。そこで語られる子ども達の言葉に共感したり、驚いたり。
「学校に行けない僕を、親は精神科に連れて行った。僕はその当時偏見を持っていて、精神科に行くのは廃人だと思っていた。そしてホッとした。廃人になった僕に、もう誰も学校に行けと言わないだろうと思ったから」
そう語る彼のかつての苦しみ、絶望、そこからこうして大人たちの前で自分の気持ちを語るようになるまでの歩みを思うと、涙なしに聞くことはできませんでした。
私自身は、有り体にいえば、いちいち深く考えすぎる、感受性が敏感すぎる、面倒臭い子どもでした。
でも、去年、子どもの権利などのために力を尽くされている弁護士の山下敏雅さんという方の記事を拝見し、その中の一文に頭を殴られたようなショックを受けました。
「○○の生徒という所属や属性の枠に、子どもたちを合わせようとするのは『支配』です。自分の頭で考えて育っていくことにつながりません」
あの当時の私が皮膚で感じ、違和感を覚え、拒絶していたのは、この「支配」に対するものだったとストンと胸に落ちたのです。そして、恐らくは、手紙をくださった恩師が感じていたものも。
もちろん、不登校には様々な理由があり、私もまたその一例に過ぎません。
が、枝野代表がツイッターの返信でその後書かれた通り、
「不登校の背景には、本人や保護者の責に帰すことのできない様々な事情がある」ことを多くの人に知っていただきたい。
かつての当事者としてそう強く思います。
大学卒業後、フリースクールのボランティアスタッフとして活動してきました。かつての私のように学校にいけなくて苦しい、学校には行きたくないけれども友達とは遊びたい、勉強したい、という思いの子ども達の力になればとの想いからです。不登校をしていたとき、不安で仕方がなかった自分の将来。そのことを思うと、具体的に力になることはできなくとも、不登校を経て、大人になって、元気にやっている私の姿があるだけでも、子ども達や保護者の方になんとなくほっとしてもらえるかなとの思いがあったからでもあります。私自身が、そのような役に立てたのかはわかりませんが、同じ苦しみを抱える子ども達と接することによって、同じ思いを抱えていたのは私だけではなかったと改めて感じ、もう一段、深く当時の自分を肯定することができ、苦しい経験も無駄ではなかったと思うことができるようになりました。
いままさに、不登校に悩んでいるお子さん、親御さんに僅かでも想いが届くことを願って。
写真は、ある学校の標語。
「柔軟に考えよう」
フリースクール、そして多様な教育への想いはまたの機会に譲りたいと思います。